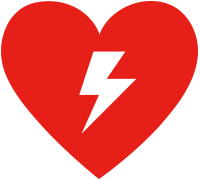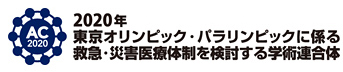指導医認定制度
指導医認定制度規則施行細則
第一章 総 則
| (目的) |
| 第1条 |
本細則は、日本蘇生学会指導医認定制度規則(以下「規則」という。) 第20条の規定に基づき、日本蘇生学会指導医認定制度の実施に関して必要な事項を定める。 |
第二章 認定の申請
| (申請資格) |
| 第2条 |
蘇生学会指導医の認定を受けることができる者は、以下の各号を満たす者とする。
| (1) |
医師(歯科医師を含む)免許取得後5 年間以上の臨床経験を有していること |
| (2) |
申請年を含めて過去3年間分の会費を納入し継続して、本会の正会員であること |
| (3) |
蘇生学に関する十分な知識と技能を有していること |
| (4) |
蘇生学に関する教育および指導に当たっていること |
| (5) |
業績に関して学会が定める所定の単位を修得していること |
| (6) |
アメリカ心臓協会二次救命処置(AHA-ACLS)、アメリカ心臓協会小児二次救命処置(AHA-PALS)、日本救急医学会二次救命処置(ICLS)、日本内科学会認定内科救急(JMECC)の他、二次救命処置を含む心肺蘇生法研修コースのうち、本学会が認定するコースの修了資格を有するもの |
|
| (申請書類) |
| 第3条 |
申請者は、以下の書類を学会に提出しなければならない。
| (1) |
日本蘇生学会指導医認定申請書 |
| (2) |
履歴書 |
| (3) |
会員歴証明書(事務局が用意する。申請時に添付する必要なし) |
| (4) |
業績目録 |
| (5) |
蘇生法・蘇生学の教育および指導に関する実績を示すもの |
| (6) |
本学会が認定する、二次救命処置を含む心肺蘇生法研修コース修了の資格を証明する書類 |
|
| 2 |
前項に規定する(1)から(4)の書類は、本会の定めた所定の用紙とする。 |
| (審査料) |
| 第4条 |
申請者は、第3条に規定する書類とともに審査料を納めなければならない。 |
2 |
審査料は、10,000円とする。 |
| (申請期間) |
| 第5条 |
申請の受付期間は、原則として毎年4月1日から6月30日までとする。 |
| 2 |
認定委員会は日本蘇生学会雑誌「蘇生」に蘇生学会指導医の申請について公告する。 |
| (会員歴証明書) |
| 第6条 |
本会は、申請者に会員歴証明書を交付するものとする。 |
| (業績目録) |
| 第7条 |
業績目録には、別表に示すところにより50単位以上の蘇生学に関する業績を記載するものとする。ただし、50単位のうち、日本蘇生学会学術集会への出席による単位40単位以上を含まなければならない。 |
| (単位の証明) |
| 第8条 |
業績目録にかかる修得単位の証明は、申請年の3月31日までの5年間の以下の各号に掲げる書類によるものとする。
| (1) |
大会出席にあっては、当該大会の参加証明書あるいはその写し |
| (2) |
大会における発表にあっては、当該発表の抄録の写し |
| (3) |
学術論文にあっては、当該論文の別刷あるいはその写し |
|
| (教育および指導に関する実績) |
| 第9条 |
教育および指導に関する実績とは、医療関係者、学生および一般の人々に対する蘇生に関する講義ならびに実習等の実績をいう。
(実績証の発行がない場合には、実施日時、受講者数、講義ならびに指導実習内容、対象者、継続性などを示した自作の資料で代用する) |
第三章 認定の審査
| (審査の実施) |
| 第10条 |
蘇生学会指導医の認定の審査は、規則第7条に基づき日本蘇生学会指導医認定委員会(以下「認定委員会」という)が行う。 |
| (審査の方法) |
| 第11条 |
認定委員会は、申請者の提出した書類により認定の資格を審査する。 |
| 2 |
認定委員会は、申請者の提出した書類に疑義があるときは、申請者に追加資料の提出を求めることができる。 |
| (審査結果の報告) |
| 第12条 |
認定委員会は、審査の結果を代表理事に報告するものとする。 |
第四章 認定及び登録
| (認定) |
| 第13条 |
代表理事は、認定委員会の審査結果を申請者に通知するとともに合格者に蘇生学会指導医の認定を行う。 |
| (登録) |
| 第14条 |
蘇生学会指導医の認定通知を受けた者は、登録料とともに所定の登録申請書を提出する。 |
| 2 |
登録料は、10,000円とする。 |
| (認定証の交付) |
| 第15条 |
代表理事は、登録の申請者を「日本蘇生学会指導医」(以下「蘇生学会指導医」)として登録を行い、認定証を交付する。 |
| (認定の公告) |
| 第16条 |
代表理事は、認定証を交付したものの氏名を「蘇生」誌および日本蘇生学会ホームページに公告する。 |
第五章 更新の申請・審査・認定・登録
| (更新の申請) |
| 第17条 |
規則第12条ならびに第13条に基づき蘇生学会指導医の認定を更新しようとする者は、定められた期間内に申請書を本会に提出しなければならない。 |
| 2 |
更新の申請ができる者は、申請時に蘇生学会指導医の認定を受けている者で、申請年の3月31日までの5年間に50単位以上の蘇生学に関する業績を有するものとする。ただし、50単位のうち、日本蘇生学会学術集会への出席による単位40単位以上を含まなければならない。 |
| 3 |
申請に必要な書類は、本細則第3条に準ずる。ただし、第1号の申請書は、日本蘇生学会指導医認定申請書とする。更新申請には、本細則第3条のうち(3)と(6)の提出を免除する。 |
| 4 |
更新認定のための審査料は、10,000円とする。 |
| 5 |
申請の受付期間は、原則として毎年4月1日から6月30日までとする。 |
| 6 |
その他更新の申請に必要な手続きは、本細則第二章「認定の申請」の規定によるものとする。 |
| 7 |
満65歳以上の正会員または名誉会員、功労会員については、更新申請書提出時に業績目録、単位の証明、教育に関する実積の記載を必要としない。 |
| (更新猶予の特例) |
| 第18条 |
更新にあたり特別の理由で前条第2項の条件に満たない者は、有効期間満了年の申請期間に以下の各号に掲げる書類を認定委員会に提出しなければならない。
- (1)指導医更新猶予申請書(書式自由)
- (2)更新猶予の申請理由を証明するもの
|
| 2 |
猶予期間は最大2年とする。 |
| (更新猶予を受けた者の更新申請) |
| 第19条 |
前条により、更新猶予が認められた者は、猶予期間満了の年の申請期間に、細則17条に定める手続きをとらねばならない。
なお、その際提出する業績目録は猶予期間とそれ以前の5年間の業績で規定の50単位を満たさなければならない。 |
| 2 |
更新が認められた場合、次の更新時期は5年後として、通常更新時と同様の審査を行う。 |
| (更新の審査) |
| 第20条 |
蘇生学会指導医の資格の更新の審査は、認定委員会が行う。 |
| 2 |
更新の申請者に対する審査は、本細則第三章「認定の審査」の規定により行う。 |
| (更新の認定及び登録) |
| 第21条 |
代表理事は、認定委員会の審査結果を更新申請者に通知するとともに合格者に蘇生学会指導医の認定を行う。 |
| 2 |
代表理事は、登録の申請者を蘇生学会指導医として登録し、認定証を交付する。 |
| 3 |
登録手数料は、10,000円とする。 |
| 4 |
代表理事は、認定証を交付した者の氏名を「蘇生」誌および日本蘇生学会ホームページに公告する。 |
第六章 補 則
| (実施要領) |
| 第22条 |
認定委員会は、本細則に定めるほか、蘇生学会指導医の認定及び更新認定を円滑に実施するために必要な事項を実施要領として制定することができる。 |
| (細則の改正) |
| 第23条 |
本細則の改正には、本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。 |
附 則
本細則は平成8年10月5日より施行する。
本細則は平成17年11月4日より施行する。
ただし、第2条(6)、第3条(6)および、第17条2のうち心肺蘇生法研修コース修了の資格については平成19年度から施行する。
平成16年度までの日本蘇生学会蘇生法指導医は日本蘇生学会指導医とよみかえるものとする。
本細則は平成18年12月2日より施行する。
本細則は平成25年12月1日より施行する。
本細則は令和3年11月12日より施行する。
(別表)
| 区分 |
学会・学術雑誌等の種別 |
単位数 |
| 1 学術集会出席の場合 |
日本蘇生学会学術集会 |
20 |
| その他の関連学会学術集会 *1) *2) |
5 |
| 2 学術集会発表の場合 |
日本蘇生学会学術集会での発表 |
10 |
| その他の学術集会での蘇生に関連する発表 |
5 |
| 3 学術論文の場合 |
「蘇生」誌に掲載された論文 |
10 |
| その他の学術雑誌などに掲載された蘇生に関連する論文 |
5 |
学術集会での発表及び学術論文の発表は、発表者、共同発表者にかかわらず同じ単位数とする。
- *1)日本蘇生協議会(JRC)に加盟している学会
- *2)日本蘇生協議会(JRC)が主催する学術集会
(平成 8年10月 5日制定)
(平成10年 9月25日改正)
(平成13年10月25日改正)
(平成15年11月 6日改正)
(平成17年11月 6日改正)
(平成18年12月 6日改正)
(平成21年 2月28日改正)
(平成22年 9月 9日改正)
(平成25年12月 1日改正)
(令和 4年11月 5日改正)
(令和 5年11月18日改正)
(令和 6年12月 6日改正)